vol.53 ヘッドホンユーザーの方へ 耳を守るための新習慣
2025.02.07あなたの耳は聞こえていますか?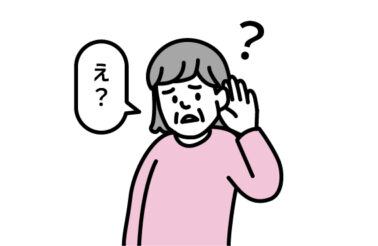
子どもの頃、祖母の家に遊びに行くと、玄関に入るなりテレビの音が響いていました。
祖母と母が電話で話をしていると、母と同じ部屋にいる私にも祖母の声が聞こえます。
聞こえにくいため、声が自然と大きくなってしまうようです。
加齢とともに聞こえにくくなるのは主に高音域で、難聴の患者数は約1,430万人(国民全体の約10%)だそうです。胎児の頃の影響や中耳炎などの耳鼻科疾患、耳垢の蓄積、動脈硬化による血流の変化、さらに騒音などの環境因子が加わることで難聴は進行します。
ところが、今や難聴は高齢者だけの問題ではなくなっています。
7万人を超える聴力データの分析
2000年から2020年まで、国立病院機構東京医療センター耳鼻咽喉科で約7万件の聴力検査データが収集されました。※1 このデータには、10歳代から90歳代までの年齢層が含まれており、1万人を超えるデータベースが構築されています。年代別の平均値が男女別に示され、聴力の実態が明らかになっています。
改善していた聴力
この研究を前半と後半に分けて、平均値の比較や時系列解析を行ったところ、年齢が高くなるにつれて個人差は大きくなるものの、高音(8000Hz)の聴力は全年齢層で改善していることがわかりました。この改善は、喫煙率の低下や生活習慣病の治療の普及、健康意識の高まりなどが影響していると考えられています。
心配なのは40歳代以下
一方で、新たに示されたデータによると、4000Hzの聴力は40歳代以下の世代で徐々に悪化していることが明らかになりました。
通常の話し声は300~3000Hz程度の音域です。4000Hzは話し声よりも高めの音で、ピアノの高音や鳥の鳴き声くらいの高さの音です。
音の振動を脳に伝える役割を果たしているのは「有毛細胞」です。しかし、大きな音量で音楽などを聞き続けると、有毛細胞が徐々に壊れていきます。一度失った聴覚は戻りませんし、徐々に進行するため気づきにくい場合が多いとされています。
4000Hzの周波数の聴力低下は、持続的な騒音暴露による影響を受けやすいため、ポータブル音楽デバイスの普及が一因と考えられています。特にヘッドホンやイヤホンは耳の中に直接音が届くため、長時間聞き続けることで難聴を引き起こすリスクが高まります。
対策1:音量制限
WHO(世界保健機関)によると、80dBの音量を1週間に40時間以上、90dBの音量を1週間に4時間以上聞き続けると難聴のリスクがあるとされています。
そのため、イヤホンやヘッドホンの音量は80dBよりも低い音量に保つことが推奨されます。イヤホンの音量を確認するアプリを使って、自分が聞いている音量をチェックするのもおすすめです。また、スマートフォンには音量制限機能が付いている場合があるため、設定を活用しましょう。
さらに、低い音量でもしっかり聞こえるように、フィット感の良いイヤホンやノイズキャンセリング機能がある機器を使うことも効果的です。
騒音が大きな場所にいる必要がある場合は、耳栓を使うのも良い方法です。
対策2:大きな音を聞く時間を減らす
大きな音量で聞き続けると、有毛細胞が徐々に壊れていきます。それを守るためには、音を連続して聞かない、適度に休憩を取る、といった予防策が重要です。連続してイヤホンを使用せず、休憩を挟むことで耳を休めることが大切です。
対策3:定期的に聴力を確認する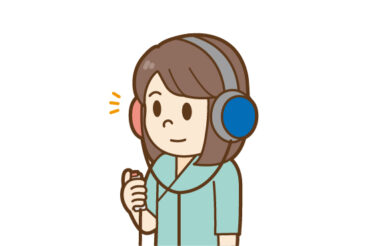
職場の定期健診を受けている方は、聴力検査があります。徐々に変化している聴力は自分では気づきにくいことが多いため、客観的に聴力を確認できる定期的な検査は非常に重要です。
加齢とともに進行する難聴
加齢とともに難聴は進行します。聞こえにくくなることでコミュニケーションに支障をきたすため、近年では難聴が認知症のリスクと関連している可能性も指摘されています。
人生100年時代を迎えた今、聴力へのケアは健康を維持する上で欠かせない要素です。早めの対策を心がけましょう。
参考:
※1 和佐野浩一郎、加我君孝、小川郁 10代から90代までの男女別聴力変化パターン The Lancet Regional Health -Western Pacific(電子版)
eヘルスネット ヘッドホン難聴(イヤホン難聴)について
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/sensory-organ/s-002.html



